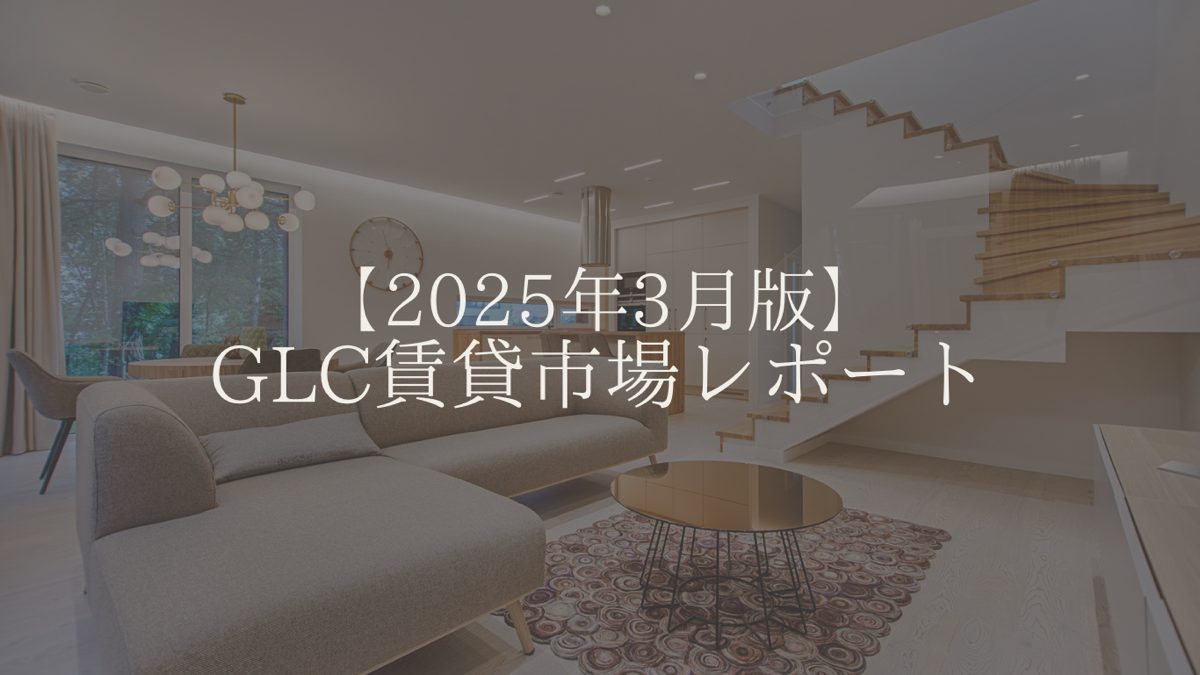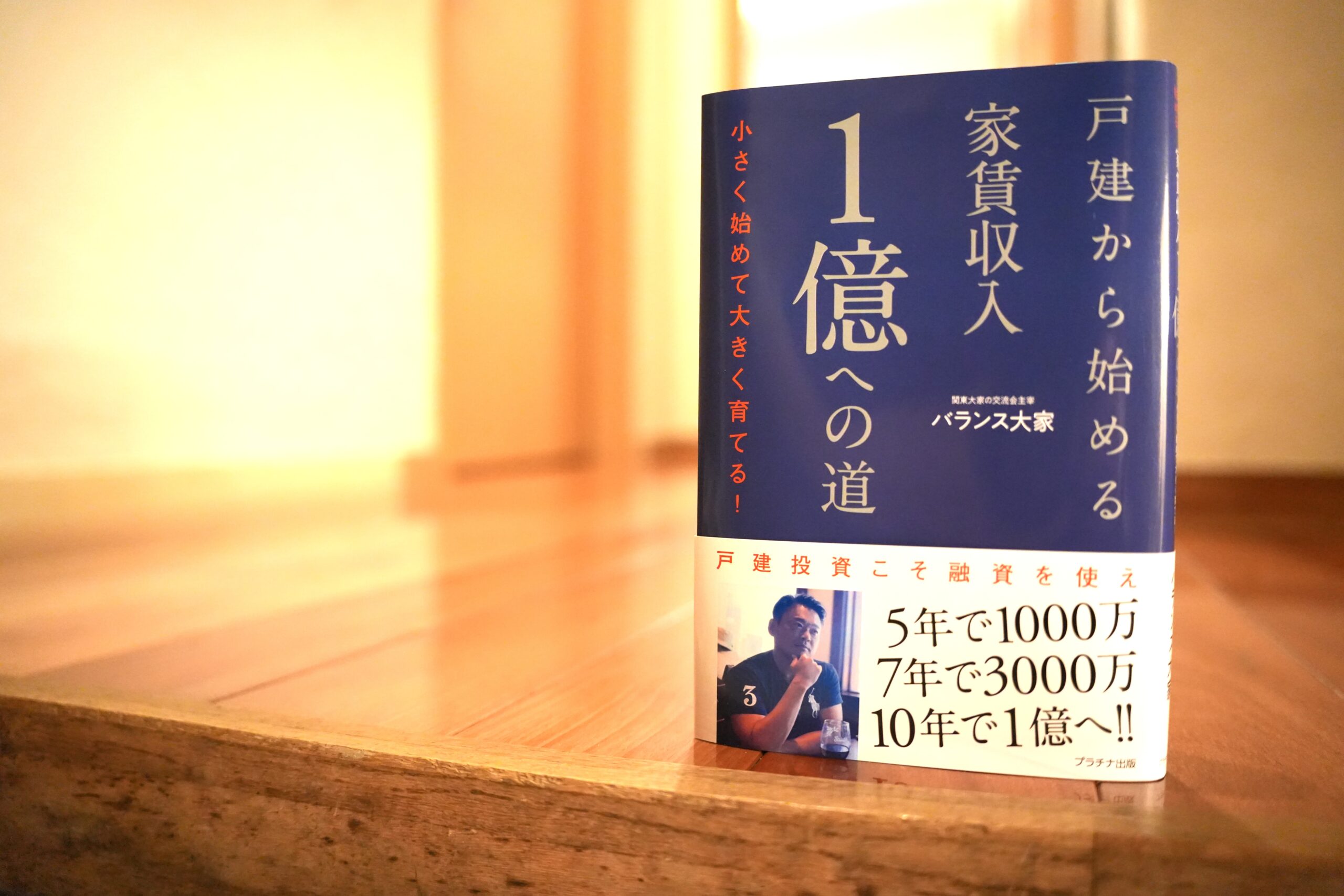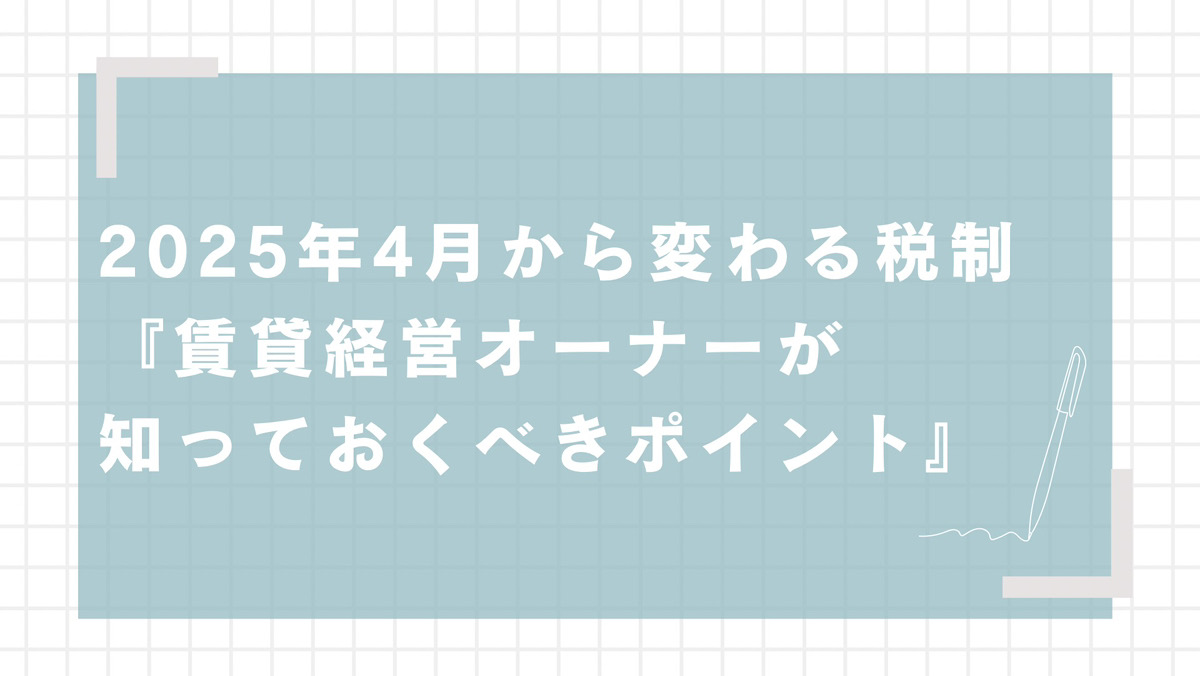
【2025年4月から変わる税制】賃貸経営オーナーが知っておくべきポイント
2025.3.25
2025年4月、令和7年度税制改正が施行され、不動産賃貸経営に関わるオーナーにとっても税制の変更が予定されています。政府が発表した「税制改正大綱」に基づき、賃貸経営に直接的・間接的に影響を与えるポイントを詳細に解説します。
今回は、税負担の軽減策から管理体制の見直し、さらには家族経営やスタッフ雇用に関わる改正まで、賃貸オーナーが押さえておくべき情報を網羅的にご紹介します。
(目次)
- 老朽化マンション対策の強化:建替え・修繕がしやすくなる
- 大規模修繕に伴う固定資産税の減額措置が継続&手続き簡素化
- 中小企業経営強化税制の拡充:設備投資のチャンス
- 「103万円の壁」の見直し:家族やスタッフの働き方に影響
- 給与所得控除の最低保障額引き上げ:スタッフ雇用にプラス
- 今後の展望:令和8年度以降も見据えて
- まとめ:変化をチャンスに変える準備を
1. 老朽化マンション対策の強化:建替え・修繕がしやすくなる
日本では老朽化したマンションの増加が社会問題となっており、2025年4月からの税制改正では、この課題に対応する措置が強化されます。具体的には、「マンション除却組合」「マンション再生組合」「マンション等売却組合」といった組織が公益法人等とみなされることで、収益事業以外の所得に対する法人税が非課税となる制度が導入されます。この措置は、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の改正と連動しており、特に築年数が長い物件を所有する賃貸オーナーにとって注目すべきポイントです。
具体的な内容
例えば、築40年以上のマンションを所有している場合、建替えや大規模修繕を検討する際に、これらの組合を設立することで税負担が軽減されます。通常、建替えには多額の資金が必要となり、組合運営に伴う収益(例えば寄付金や管理費の一部)が課税対象となるケースもありましたが、新制度ではこうした所得が非課税となるため、実質的なコストダウンが期待できます。また、組合を通じて住民や区分所有者との合意形成がしやすくなり、スムーズなプロジェクト進行が可能になります。
影響と対策
区分所有の賃貸マンションを保有するオーナーにとって、老朽化対策がより現実的な選択肢となるでしょう。物件の資産価値を維持・向上させるため、管理組合と連携して建替えや修繕の計画を早期に策定することが重要です。特に、空室率の上昇や修繕費の増加に悩んでいる場合、この税制優遇を活用して物件の競争力を高めるチャンスです。まずは管理組合の総会で議題に上げ、専門家(税理士や不動産コンサルタント)に相談しながら具体的なシミュレーションを行うことをおすすめします。
2. 大規模修繕に伴う固定資産税の減額措置が継続&手続き簡素化
マンションの長寿命化を促進するため、大規模修繕工事に伴う固定資産税の減額措置が2025年4月からさらに2年間延長されます。加えて、手続きの簡素化が図られ、管理組合が市町村に必要書類を一括提出すれば、個々の区分所有者が個別に申告する手間が省けるようになります。これまでは、各オーナーが自分で申請する必要があり、煩雑さがネックとなっていましたが、新制度ではその負担が大幅に軽減されます。
具体的な内容
減額措置の対象となるのは、耐震改修や省エネ改修など、一定の要件を満たす大規模修繕工事です。例えば、外壁の補修やエレベーターの更新、給排水管の交換などが該当します。工事完了後の翌年度に固定資産税が一定割合(通常は1/2~1/3程度、地域による)減額される仕組みで、延長により2027年3月まで適用が可能です。手続き簡素化により、管理組合が主体的に動けば、オーナー側の手間はほぼゼロに近づきます。
影響と対策
この改正は、築20~30年以上の物件を所有するオーナーにとって特に有利に働きます。大規模修繕は資金面での負担が大きい一方、物件の価値維持に不可欠な投資です。減額措置を活用すれば、実質的なコストが抑えられ、入居者にとっても住環境の向上が期待できます。対策としては、修繕積立金の状況を確認し、2025年度中の工事実施を視野に入れた計画を管理組合と共有することです。また、市町村ごとの具体的な要件や減額割合が異なるため、自治体のホームページや窓口で詳細を確認しておくと安心です。
3. 中小企業経営強化税制の拡充:設備投資のチャンス
中小企業を支援する「中小企業経営強化税制」が拡充され、法人形態で賃貸経営を行うオーナーにメリットをもたらします。新制度では、雇用者給与を3%以上増加させる方針を「経営力向上計画」に盛り込んだ場合、設備投資にかかる取得価額の4分の1まで特別償却または税額控除(上限あり)が受けられます。
具体的な内容
例えば、賃貸管理を効率化するためにIoT機器(スマートロックや遠隔監視システム)を導入する場合、1,000万円の設備投資を行ったとします。この場合、250万円分を特別償却として経費計上するか、一定額を税額控除として法人税から差し引けます。ただし、適用には給与総額の増加が条件となるため、スタッフの雇用や給与見直しが必要です。
影響と対策
個人事業主ではなく法人形態で賃貸経営を行っているオーナーにとって、設備投資のハードルが下がる好機です。賃貸市場では、入居者のニーズが多様化しており、防犯性や利便性を高める設備が求められています。例えば、AIを活用した入居者管理システムや省エネ設備の導入は、空室率の低下や賃料アップに繋がる可能性があります。対策としては、まず経営力向上計画の策定を進め、税理士や中小企業庁の支援窓口に相談しながら申請準備を整えることです。また、スタッフの給与増額を計画に組み込むことで、従業員満足度も向上し、一石二鳥の効果が期待できます。
4. 「103万円の壁」の見直し:家族やスタッフの働き方に影響
所得税の課税最低限が見直され、いわゆる「103万円の壁」が「160万円」に引き上げられます。具体的には、基礎控除が年収200万円以下で95万円、それを超える場合も段階的に増額され、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。これにより、年収160万円までは所得税が発生しない仕組みに。また、19~22歳の大学生等を対象とした「特定親族特別控除」が新設され、子の年収が150万円までなら親は63万円の控除を受けられ、150万円超188万円までは段階的に減額されます。
具体的な内容
例えば、家族経営で配偶者が管理業務を手伝い、年収103万円以内に抑えていた場合、新制度では160万円まで働いても税負担が発生しません。また、大学生の子がアルバイトとして物件清掃や事務作業に従事する場合、年収150万円までは親の扶養控除が維持され、税制上のメリットが得られます。
影響と対策
賃貸経営を家族で支えているオーナーにとって、働き方の選択肢が広がります。家族の手伝いを増やすことで、人件費を抑えつつ業務効率化を図れるでしょう。また、パートスタッフを雇用する場合も、従来の「103万円の壁」を意識したシフト調整が不要になり、労働時間を増やしても手取りが減りにくい環境が整います。対策としては、家族やスタッフの役割を見直し、新たな給与体系を設計することです。特に、若い世代の労働力を活用したい場合は、特定親族特別控除の条件を満たすよう、収入管理に注意しましょう。
5. 給与所得控除の最低保障額引き上げ:スタッフ雇用にプラス
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられることで、雇用するスタッフの手取りが増加します。この変更は、賃貸管理を外部委託せず、自社でスタッフを雇用しているオーナーに直接的なメリットがあります。
具体的な内容
年収100万円のパートスタッフの場合、従来は55万円の控除で課税所得が45万円でしたが、新制度では65万円の控除により課税所得が35万円に減少。所得税率5%で計算すると、年間約1万円の税負担軽減となります。少額に見えますが、複数人を雇用する場合や長期間で見ると、影響は無視できません。
影響と対策
スタッフの手取り増加は、モチベーション向上や離職率低下に繋がります。小規模な賃貸経営では、人材確保が課題となることが多いため、この改正を雇用環境改善のきっかけにできます。対策としては、スタッフに税制変更を伝え、給与体系の見直しを検討すること。特に、正社員登用や長期雇用を視野に入れた待遇改善を進めれば、経営の安定性も高まるでしょう。
6. 今後の展望:令和8年度以降も見据えて
2026年4月からは「防衛特別法人税」(法人税額の4%付加)が導入予定ですが、年間500万円までの基礎控除が設けられているため、中小規模の賃貸法人への影響は限定的と考えられます。例えば、法人税額が400万円の場合、追加負担はゼロです。ただし、収益規模が大きい法人の場合、税負担が増える可能性があるため、長期的な視点での経営戦略が求められます。
対策のポイント
法人化のメリット(節税や事業承継のしやすさ)とデメリット(税負担増や事務コスト)を再評価し、個人事業主として続けるか法人化を進めるかの判断を見直す良い機会です。特に、複数物件を保有するオーナーは、税理士とシミュレーションを行い、最適な形態を模索しましょう。
まとめ:変化をチャンスに変える準備を
2025年4月からの税制改正は、賃貸オーナーにとって税負担軽減や経営効率化に関わる部分での変更があります。老朽化対策や設備投資の優遇は物件の競争力を高め、家族やスタッフの働き方の柔軟性向上は人手不足の解消に繋がります。これらの変化をチャンスと捉え、具体的な計画を立てることが成功の鍵です。管理組合との連携や修繕計画の見直し、設備投資の検討、給与体系の調整を早めに進め、税理士や不動産専門家に相談しながら対応を固めましょう。税制の変化を味方に、持続可能で収益性の高い賃貸経営を目指しましょう。
Keyword